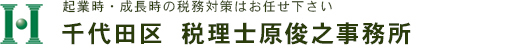起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!
営業時間 | 月~金:9:00~18:00 |
|---|
個人の確定申告の全体像
所得税においては、もうけ(所得)の種類によって税率が違うという面があるという点、
所得の種類・規模によって作業の煩雑さも変わるという面も押さえなければなりません。
1.所得の種類
所得税においては、基本的にその稼ぎの元などにより10種類の所得に分けて税金計算することとなります。すなわち、
利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・雑・山林・退職
に区分することができます。ここではあえて、難易度を考慮して、
(利子)・給与・退職・一時・配当・雑・不動産・事業・(山林)・譲渡
と区分します。
後にいくに従い、徐々に申告の難易度があがっていくこととなります。
なお、利子所得は海外のもの等特殊なもの以外については、申告は必要ないため、ここでは割愛します。
預金利子を思い浮かべていただければ分かると思います。
また、山林所得(山林の伐採又は譲渡による所得)は滅多にお目にかかれないため、これも割愛します。
2.所得税の計算の段階
法人は、基本的に【収益-費用=利益】で、この利益に一定の調整を加えた「所得」に対して税金計算するという形です。
しかし、個人の場合は、そう簡単ではありません。その理由として、様々な個別事情を税法が考慮しているからです。
継続的な勤労所得等は多く税金を課しますが、例えば、退職金や年金等は給料と同じようには税金を課さないということ等がその理由として考えられます。
計算の段階として、
- 収入の種類ごとの計算
- 収入の合算
- さまざまな控除の計算
- 税金計算の元となる金額の計算
- 税金の計算
という5段階となっています。まず、
(1) 収入の種類ごとの計算
上記1.に挙げた儲けの種類ごとにそれぞれ金額を算出します。
これが、個人の計算においても最も重要なステップとなります。
次に
(2) 収入の合算
儲けの種類ごとの金額を合算計算します。
ここでは、似たもの同士の所得はひとつにされます。また、損を他の儲けと相殺するのもこのステップです。
(3) さまざまな控除の計算
その後、儲けから様々な控除を行います。
例としては、保険料の控除や医療費の控除などがこれにあたります。
(4) 税金計算の元となる金額の計算
(3) の後に一定の調整等が行われ、税金の対象となる元の金額を算定します。
(5) 税金の計算
最後に税金計算を行います。ローン控除等の税額控除はこのステップで控除します。
3.所得計算

(1) 給与所得
勤務先からのお給料になります。源泉徴収票に基づき、申告書に記載するだけなため最も
簡単です。
複数の勤務先から給与がある人は、それらを合算して申告することとなります。
他に稼ぎがなく1ヶ所給与の人で2,000万円以下の人は、原則として申告は必要ないのですが、医療費控除等を適用するため、申告することもあります
(2) 退職所得
勤務先からの退職金となります。
これも、源泉徴収票に基づき、申告書に、記載するだけのため、簡単です。
なお、退職所得については、基本的に源泉徴収で納税が終了するため、原則申告は必要ありません(例外として申告が必要な場合もあります)。
但し、他の所得との兼ね合い(他の所得で損がでており、退職所得から控除する場合や他の所得で保険料控除等を引ききれないため、退職所得から控除する場合等)で申告することが有利なこともあります。
分離課税ですので、給与等とは税金計算を別に行い最後に税額を合算します。
なお、税制改正により、短期勤続の場合は従来の税額より不利となりますので、
退職時期等も税金では考慮できると理想的です。
(3) 一時所得
一時所得とは、他の所得に該当しないもので、一時に受ける所得のうち、労務の提供や資産の譲渡対価等に該当しないものになります。
一時所得で代表的なものは、満期保険金になります。その他にも借家人が受ける立退き料等該当するものもあります。
一時所得は単発の儲けで継続性がないことが考慮され50万円の控除枠があります。
さらに50万円控除後の1/2に対して課税されます。申告を忘れがちな所得です。
なお、100万円を超える保険金については保険会社等から税務署に書類が送られています。
(4) 配当所得
配当所得とは、株式等の配当をいいます。
現在では、配当は申告が不要な場合が多い状況ですが、申告が必要な場合があります。また、その人の税率によっては、申告したほうが有利な場合もあります。
事務手続きの簡略化を図るのであれば、上場株式等(5%未満所有の通常株主)は原則として申告が不要のため、申告しないことが考えられます。
しかし、他の収入状況等により、配当の申告を行い、配当控除(税額控除)の適用を受けた方が得な場合もあります。
なお、上場株式等の配当を上場株式等の譲渡との合算で分離課税の申告の選択もできます。(つまり、上場株式等の譲渡で発生した損失を上場株式等の配当所得から控除して申告も選択できます。)
(5) 雑所得
雑所得とは他の全ての所得に該当しないものをいい、年金や原稿料等がこれにあたります。
年金については、書類により明らかになるため比較的容易であります。
しかし、注意すべきは、郵便局の定期年金などを多く加入されている方は、契約ごとに何度も書類が郵送されてくる関係で、申告を洩らしてしますことがままあります。
原稿料等については少し煩雑になります。また、事業とはいえない副業なども原稿料等と同様の取扱いとなります。
これらは売上と経費を集計し、収支内訳書という決算書を作成して、税務署に提出することとなります。
(6) 不動産所得
不動産所得とは、不動産の貸付による所得です。確定申告作業におけるメイン業務のひとつです。
発生する収入としては、賃料、礼金、更新料、その他の収入(自販機収入等)といったものです。なお、敷金は収入にはなりませんが、把握しておくこと必要があります。
発生する費用としては、固定資産税、管理費、業務委託費、損害保険料、修繕費、水道光熱費、減価償却費、支払利息等です。
管理会社を通していれば、その管理会社が作成する書類で、収入や業務委託費や修繕費等を把握できます。なお、契約書をチェックすることも重要です。
固定資産取得年度は固定資産の分解作業が必要になりますので、煩雑となります。
不動産事業専用の通帳を作成して、入出金はその通帳を通すような形が宜しいかと思います。それから、物件が多い場合には、管理上の観点からも一覧表を作り、収入関係、経費関係の年間の記録を残しておくと良いかと思います。
なお、不動産事業を考える上では、損益より資金収支の方が重要です。但し、資金収支は申告作業とは直接は関係ありません。
簡単な資金の儲けの計算方法としては、利益+減価償却費+敷金収入-敷金支出-借入金元本返済です。
(7) 事業所得
事業所得とは、小売業、サービス業その他の事業から発生する所得です。計算方法は、その業種により異なります。
日常つけている帳簿を元に決算処理を行うこととなります。法人の利益計算と最も良く類似しております。
また、事業所や店舗が自宅と併用の場合には、経費の内容に応じて、床面積比や使用比率等合理的な比率で、事業用部分と家事用部分を計算します(経費按分)。
規模が大きくなってくると、法人のほうが税務上、信用取引関係、資金調達上等有利になることがあります。
規模が大きくなってきましたら、専門家に相談されることが良いかと思われます。なお、お医者様に関しては、特例計算があります。
(8) 譲渡所得
譲渡所得とは、原則として資産の譲渡による所得をいいます。これが、最も難解のうえ金額的にも大きくなるため、最も神経が必要となります。
その所有期間により短期と長期で分けることなり、また、不動産、株式、ゴルフ会員権等の種類別で税金計算が異なります。
なかでも重要なのは不動産の譲渡で、多くの特例があります。
専門家に相談されることが確実です。
4.その後の流れ
その後、合算計算、さまざまな控除の計算、税金計算の元となる金額の計算、税金の計算となります。
上記3.で計算した儲けをまず合算し、損と益の相殺等を行います。その後、医療費控除等の控除を行い、差し引き金額を算定して、税金計算を行います。
5.申告書の用紙
色々な用紙があり面倒に感じる方も多いと思います。申告書は第1表、第2表は絶対使用します。分離課税(退職所得、譲渡所得)がある場合には、第3表が加わります。
なお、損失申告の場合には、第4表をメインに使用します。
もちろん、不動産所得、事業所得、雑所得(原稿料等)が発生する人は他にも、決算書・収支内訳書等を作成する必要があります。また、他にも添付書類を作成する必要があります。
最後に、納付書を記載して税金を納付又は振替納税を利用して自動引き落としとします。(振替納税の場合は、税金の引き落としは、4月中旬くらいです。)
税金が還付となった人は、申告書に還付口座を記載し、後日税務署から税金の還付があります。
上記のような流れとなります。
6.最後に
確定申告は書類を集めるのが最も煩雑です。3月15日までまだ日があると思ってのんびりしているとすぐ期限がきてしまいます。
特に資料を紛失した際に資料の再請求等をしてもすぐに資料が入手できない可能性もあります。
青色申告特別控除は事業的規模で元帳作成している事業主は、電子申告を利用する場合は65万円(事業所得又は不動産所得の方)を取れますが電子申告を利用しないと、控除額が55万円となります。
東京都千代田区飯田橋(旧文京区) 税理士 原俊之事務所 (トップページはこちらをクリック)
お問合せはこちら

お気軽にご相談ください
お電話でのお問合せはこちら
03-5211-5945
営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)
どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!
(税務相談は来所相談に限ります)