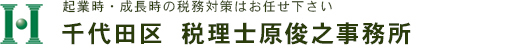起業時・成長時の融資・節税のサポートは、千代田区の 「税理士原俊之事務所」 にお任せください!
営業時間 | 月~金:9:00~18:00 |
|---|
事業のステージごとの経理の大枠の重点業務
お客様においては、開業して間もないお客様もいれば、事業開始から数年経過した
お客様、何十年も事業を行っているお客様と、お客様の事業の段階は千差万別です。
ここでは、お客様の事業がどの段階にあるかにより、重点を置くまたは留意すべき
経理の業務を参考のため、一部列挙しております。
お客様が経理について全体から考えることは、個別作業を行うことと同じように
あるいはそれ以上に重要と弊税理士事務所は考えております。
お客様の事業の段階等を考慮した、経理体制の構築につきましても、弊税理士事務所に
ご相談いただければ幸いです。
1.創業期
主目的:社長様の事務負担の軽減 → 営業活動への専念
4.後退期
主目的:スムーズな事業撤退案の検討
事業継続・撤退の検討、会社清算、営業譲渡、金融機関折衝
主目的:社長様の事務負担の軽減 → 営業活動への専念
創業期におきましては、社長様が営業・事業活動に専念できますよう社長様の
事務負担を軽減する体制を築くことが重要です。
なお、創業段階では、組織形態や経理体制を作っていかないといけないため、
これらの検討等も必要となります。
創業段階では、できるだけシンプルな形を採られる方が望ましいと思います。
<業務>
(1)設立
・初期の運転資金の検討
・役員構成及び役員報酬支給額の検討
・会社と社長他親族との賃貸借等の検討
・資金繰り計画の検討
・その他、事業目的等の登記上の検討等
初期の段階では損益よりまず資金収支の管理が重要です。
(2)経理体制
経理体制の検討
個別的な話ではなく、経理体制という経理の基盤の話では、税理士事務所・
会計事務所の支援は必須です。
経理体制の検討では、経理においてどのような事務手続きを要するかをまず
一覧表にしたうえで把握して、どこまでを税理士事務所・会計事務所にご依頼いただくか、
どこまでをお客様自身が行うかという分析が必要です。
この分析作業も税理士事務所・会計事務所に依頼すれば、税理士事務所が原案を
作成して、お客様と相談の上、業務分担の検討をすることができます。
お客様が日々行っていただく業務を始め、お客様が行う作業を行なう諸業務に
関しても税理士事務所・会計事務所との顧問契約によりサポートを受けることができます。
特に創業間もない場合には、事業規模や人員も流動的に変化しますので、当初
から完全に形を作るのは難しく、順次経営体制を機動的に変えていく必要があり、
経理も例外ではありません。
顧問契約の過程で、順次、経理体制の見直し等も行なっていくこととなりますが、
抜本的な検討ですと、顧問契約と別途の依頼が必要となる場合もあります。
(3)社会保険・労働保険
新規社会保険手続
設立段階では、事業継続段階に比較しまして、各種届出等がより多く必要となる
場合が多い状況であり、社会保険(雇用保険等の労働保険も含む。)も例外ではありません。
税理士事務所では、お客様の状況にあった組織形態のご相談に応じつつ、その
雇用形態等にあった、手続作業をご提案させていただくことも可能です。
社会保険手続は本来税理士事務所の業務ではございませんが、顧問先に関しては
社会保険手続の業務のお手伝いをすることも可能です。
2.成長期
主目的:事業関連節税、資金調達、月次損益の把握
成長期におきましては、事業の成長に各種の管理活動が追いつかなくなってきます。
これは、社長様の目が組織全体に行き届かなくなることが主たる原因です。
また、特に事業が急激に拡大している局面では、利益は計上されても、先行投資としての、
従業員の雇用、設備投資その他諸々の出金が増加していくことが多く、その一方で
増加している売上の入金は、1ヶ月後~数ヶ月後というケースがほとんどですので、入金は出金に
比較して遅くなりがちです。
このような時期には、残るお金以上に数字上の利益が計上されがちなため、資金が
不足しても、税金も相当額発生することもあります。
この段階では、事業成長のための資金の確保のための節税対策、資金調達の検討、
また、月々の変動する損益の概要を適切に掴むこと。
これらの業務が最重要課題と考えられます。
<業務>
(1)節税・税金対策
「勘定合って銭足らず」この時期には、まさにこの言葉があてはまります。
数字では利益が計上されますが手元資金はそれほど潤沢ではありません。
ただし、利益が計上されていれば、それに対応した税金が当然発生いたします。
そこで、生き残りと事業拡大の損援のため、採用可能な様々な節税・税金対策
を順次、検討する必要があります。
(2)税務調査対策
税務調査は、利益が毎期安定して発生している会社であれば、3~5年に1回は
まずあります。また、業種によりそれ以上のサイクルで税務調査がある場合があります。
なお、個人事業主に関しましても、業種やその規模等により税務調査があり得ます。
税務調査は、通常の中小法人では、1日~3日程度の日数で税務署職員が訪問する状況
が多いようです。
税務調査は、納税者に精神的負担となり、また、少なくない時間を取られます。
税務調査においていくつか方針はありますが、
☆早期に終了させたい
☆グレーゾーンについて税務署の言い分は認めたくない
この2点のバランスを考えつつ、対策案を考えることとなります。
税務調査では、税理士事務所の支援が必須です。
弊税理士事務所としては、税務調査前及び税務調査期間中にお客様と打ち合わせのうえ、
お考えを伺いつつ、ご要望にあった選択肢を考え、事前の対策、税務当局との交渉等
により、お客様にとって最適な結果となるよう努力いたします。
(3)月次決算体制構築支援
事業が成長する過程では、管理が追いつかなくなってきます。
このような段階においてこそ、事業の損益状況を月々把握しつつ、資金の状況等との
バランスを見ることが重要となってきます。
事業が成長する段階では、本年の損益状況は、前期や前々期のものとは大きく異なる
のが通常です。
したがって、できるだけ早く損益の概要を掴むことが望まれます。
節税対策を行うにしても、まず現状の損益及び資産負債の状況と今後の予想を把握
することがまず前提となり、節税対策を検討するにも、できるだけ早く損益状況を
掴めると早期に対策を打つことが可能となります。
会計入力を税理士事務所・会計事務所に依頼していた場合に、会計入力関係資料を
税理士事務所等に渡していると思いますが、
☆税理士事務所等が会計入力にとりかかるまでの時間
☆取引内容の質問とその回答
☆税理士事務所内での会計入力結果の分析等
これらの作業を要することから、それなりの時間がかかります。
作業の遅い税理士事務所では、資料入手から試算表の作成まで何週間も要する
ところもあるようです。
そこで、
●早期の損益把握
●早期の節税対策
これらの目的のためには、お客様が会計入力を行うことが望ましいものです。
いわゆる、「自計化」といわれます。
自計化では、
お客様で会計入力をしつつ、税理士事務所担当者が訪問させていただき、帳簿書類
のチェック、取引内容のご質問等をさせていただき、お客様の会計入力が税務上及び
会計上、望ましいかという観点からチェックさせていただき、必要があれば、修正等
をご指摘させていただくこととなります。
お客様が自計化されていれば、上記
☆税理士事務所等が会計入力にとりかかるまでの時間
☆取引内容の質問とその回答
☆税理士事務所内での会計入力結果の分析等
という問題点が相当解決され、日々において随時会計入力を行うことから早期に
帳簿書類が完成いたします。
会社規模がある程度大きくなってくれば自計化されるのが通常であり、会社の成長
には欠かせません。
したがいまして、この段階におきましては、自計化をお勧めします。
もちろん、事業規模が小さい場合、取引内容がシンプル等の場合には、あえて自計化
する必要が無い場合もあります。
(4)諸規程の検討
従業員数が10人を超えると法律上、就業規則の作成を要することとなります。
就業規則では、給与規程・退職金規程・慶弔見舞金規程等を包含することとなりますが、
これらの規程は、税務上の人件費の取り扱い等に影響してきます。
労務関係の規程自体は、基本的に社会保険労務士の守備範囲でありますが、
これらの規程を労働基準監督署に提出するとなると、会社はその内容に縛られる
こととなります。
したがいまして、その規程の内容を、税務上の観点・経営上の観点から
社会保険労務士とは別の角度から分析することも必要かと思います。
特に、退職金に関しては、適格退職年金を始め、退職金源資の運用不足により、
多くの会社が簿外の退職金債務に苦しんでいる状況です。
なお、役員退職金を支給する場合には、通常、役員退職慰労金規程を整備しておく
ことが通常です。役員退職慰労金は、税務上優遇されており、その容認される支給限度
も存在します。
役員退職慰労金は、所定の手続を踏み、容認される金額の範囲内であれば、
支給する法人において経費に算入され、支給される個人においては退職所得の分離課税
として(死亡退職の場合は、原則、所得税等ではなく、相続税の退職手当金等として、
一定額の非課税枠有り。)優遇されます。
通常、オーナー社長には、多額の退職慰労金が支給されるのが通常ですので、
相続対策や手取金額の計算等において、役員退職慰労金は重要な役割を占めます。
(5)別会社等設立検討
事業規模の拡大に伴い、利益も計上され、税金の額も増加していきます。
このような状況におきましては、別会社の設立をされると税金対策上、有効な場合が
あります。
また、ご家族の将来を考慮し、ご家族様を別会社の役員に就任させ、ご家族の将来
の対策の一環として行なうことも考えられます。
①法人税、事業税の軽減税率
中小法人の法人税・事業税におきましては、
年間の所得が800万円までの部分は年間所得が800万円を超える部分より税率が15%くらい安いです。
したがいまして、別会社に適法に所得を移転することが可能であれば、
法人税・事業税を年間約120万円程減少させられる可能性があります。
②所得の分散効果
取引実態と金額的妥当性を満たせば、同族間取引も税務上も許容されます。
また、事業の一部を別会社に移管することも可能です。
別会社に諸手法で所得を移転し、その別会社から役員報酬等により、ご家族に財産を
移転する方法もあります。
なお、非常勤役員に関しましては、通常、多額の役員報酬の支給は難しい部分が
ございますが、多くの会社について、各会社の経営責任や業務責任を負うことで、
各会社からのそれぞれある程度の役員報酬を支給することもできます。
③損益管理、事業管理の明確化
会社が別々であるということは、当然のことながら、各会社で管理体制が必要と
なり、また、決算も別々に行なうことなります。
ここで、節税という観点以外の事業上の観点から、事業ごとの損益を明確化させ
るため、後継者ごとに会社を分けるため等から、別会社化を行なうことも考えられます。
事業ごとの損益を把握するためには、別会社化の他、部門別会計の導入という手法
もあります。
但し、部門別会計では、特に、部門別の把握や本社経費などの共通費の配賦等に
おいて、明確に区分することは難しい部分もあります。
また、別会社化しても、同族間では、なかなか事業責任を明確化することは、
難しい場合もあります。
④相続への影響
相続におきましては、オーナー社長の財産として、その所有している会社の株式
の評価額が加算されます。
非上場株式の税務上の評価方法は複雑であり、現在の規定では、会社規模が縮小
すると逆に株式の評価額が上昇することもあります。
したがいまして、事業上の観点、法人税・事業税の対策から別会社化することも
考えられますが、あわせて、将来のご相続の観点からも検討したうえで、別会社化
することが望まれます。
(6)資金調達の検討
資金調達におきましては、資金の必要額の計画、その資金の使用計画、資金の返済計画、
金融機関との交渉等が必要となります。
資金調達には、借入、増資、社債の発行などいくつか方法はございますが、
一般的な中小法人ですと、銀行からの借入がほとんど全てといって過言ではありません。
銀行により、融資の基準や姿勢が異なる部分もございますが、一番重要なことは、
資金をきちんと返済する能力があり、実際に返済する。ということを納得させることです。
したがいまして、銀行との交渉の前に、まずは、年間の資金収支の実績の洗い出しと
予想の計画、事前の資金の必要額の計算、資金使途(運転資金、設備資金等の別と
その具体的な細目等)等の練り上げをすることが望ましいものです。
また、当然のことながら、担保を要求されることがほとんどです。
担保には、人的担保(社長等が連帯保証人となること)、物的保証(自宅などの不動産
に対して抵当権を付すること)が通常要求されます。
こちらとしては、当然、できるだけ担保提供は少なくしたいものですが、
逆に金融機関としては、当然のことながらできるだけ多くの担保提供があるほど
望ましい状況です。
したがって、どこまで金融機関の担保要求に応じられるかということも検討する
必要があります。
なお、一部の借入に関しては、担保の要件が緩いものもありますので、そのような
借入を利用することも考えられます。
3.成熟期
主目的:事業承継、節税(相続関連、事業関連)
成熟期におきましては、通常、事業は比較的安定しており、今後の後継者への
事業の移転のための諸検討をしておくことが望ましいものです。
また、事業の統合(合併)や後継者が1人でないときの会社の分割等の組織再編の
検討も必要な場合もあります。
その他、トップの退職に伴い、その退職金等もあわせて検討材料となります。
<業務>
(1)相続対策
事業承継対策では、税金面と損配面の両面を考慮しつつ、事業を後継者にスムーズに
移転するための諸対策を検討・実行していくこととなります。
まず、現状の相続財産・相続税額の概算を算出し、その後、対策案等を検討いたします。
相続対策は、一度に全て終えるものではなく、段階を踏んで行なうのが望ましいものです。
また、状況変化や税制改正もありますので、何年かに一度は見直すことをお勧めします。
オーナー社長の意向を最優先しつつ、今後の後継者への事業の移転を検討すること
となります。
(2)組織再編の検討
事業が成熟期にある場合、主として、相続の観点から組織再編の検討を行なうこと
は有用です。
税金面から言えば、オーナー社長の所有する株式の株価で会社の財産価値は評価され、
相続税が課税されます。
非上場会社の株式の相続税評価額の評価方法は、税法独特のものであり、複雑で
ありますが、組織再編を行なうことで、その株式の評価額を圧縮することも可能な
場合があります。
それから、お子様が2人以上いる場合、それぞれのお子様のため、承継させる会社
を作るため、会社分割を行う方法等や、また、それが相続税に与える影響も同時に
検討が必要です。
また、事業の観点から事業を集約(合併等)を行なったり、会社分割を行なったり
する検討を行なうことも有用です。
その他、持株会社形式の組織再編の検討という考えもあります。
(3)退職金の検討と対策
事業が成熟期にある場合、後継者への事業のバトンタッチを検討されることとと
思います。
事業のバトンタッチに伴い、退職金も同時に検討されることが望ましいものです。
退職金は税制上、優遇されており、給与とは区分されて、分離課税で課税される
ことから、通常、税金は給与と比較して格安となっています。
具体的には以下の算式となります。
(退職金 − 退職所得控除額)×1/2 × 税率
さらに退職金は、税務上容認される金額の範囲内であれば、支払った法人の経費
ともなるため、会社の税金対策と同時に検討することとなります。
また、退職金の損給に伴い、会社の財産も縮小することから、会社の株式評価額に
も影響することもあり、相続税対策の上でも同時に検討することが望ましいものです。
なお、上記は、生前退職金を前提としておりますが、オーナー社長が無くなった際
の死亡退職金で退職金を支給する方法もあります。
死亡退職金は所得税・住民税の対象ではなく、相続税の課税対象となり、
また、死亡退職金は相続税の計算上、非課税枠もあるため、
生前退職金と死亡退職金のどちらが望ましいかという検討もされるとなお望ましいと
思います。
退職金は、税制上、非常に優遇されていることから、本人の税金、法人の税金、
相続税、相続の際の納税資金対策等様々な観点から検討すると多くの効果を望めます。
この検討は、事業承継対策の一環として検討することが望ましいものです。
事業承継対策に関しては、様々な角度から、シュミレーションを行なうと効果的です。
4.後退期
主目的:スムーズな事業撤退案の検討
事業継続・撤退の検討、会社清算、営業譲渡、金融機関折衝
<業務>(1)事業継続・撤退の検討
後継者が見当たらない場合や、残念ながら事業継続が難しい場合等では、事業
をこのまま継続するか撤退するかの検討が必要となってきます。
いずれの場合でも、今後の費用負担等のシュミレーションが必要となってきま
す。
一般的に、事業を継続するより、撤退する方が難しい場合が多い状況です。
これは、会社には従業員・仕入先・得意先・金融機関等の様々な関係者が関係し
ており、これらの関係者についても考慮する必要があるからです。
また、金融機関からの借入について、オーナー社長は連帯保証人となっている
ことが通常で、不動産などの担保提供もされていることが多いので、これらの担
保についての今後の取り扱いなども重要です。
したがいまして、事業継続の場合の今後の見込み、撤退する場合の費用負担、
また、撤退を前提した場合、いつの時点で撤退するのが望ましいのか、撤退の
場合の事前の対策等について、検討することが望ましいものです。
(2)会社清算
会社を清算する場合、基本的に、まずは会社解散の手続から入り、その後に清算と
いう流れとなります。
なお、会社の純残余財産がマイナスな場合、すなわち、債務超過の場合、
通常の会社清算はできません。
したがいまして、会社として、ある程度の内部留保のあるうちに事業から撤退して、
会社清算を行なう方が望ましいものです。
債務超過の場合は、他の法定清算、民事再生、破産等の手続となります。
これらの業務では、弁護士主導で業務を行なうこととなってきます。
注意点として、会社清算は登記費用等もある程度要するため、その資金負担等も
考慮する必要があります。
(3)営業譲渡
事業から撤退する場合、事業を縮小する場合、不採算部門からの撤退等では、
営業譲渡という手法も考えられます。
すなわち、会社の事業部門を譲渡する方法や、株式を譲渡することにより、
事業全ての譲渡という方法もあります。
ここで、その会社の競争の優位性として、取引先関係、ノウハウ等を営業権として、
評価を行ない、相手先との値段交渉などを行なうこととなります。
第三者への営業譲渡であれば、営業権の値段は、基本的に、交渉如何によりますが、
その交渉のための材料として、いくつかの評価のパターンとその根拠を練っておく
必要があります。
(4)金融機関折衝
事業を撤退する場合、重要なのは、会社の債務、特に金融機関に対する借入金など
の対応が重要です。
前述のとおり、債務超過であれば、通常の会社清算は行なえないことから、金融機関
との交渉も必要となってきます。
また、金融機関からの借入の場合、通常、代表者等が連帯保証人となっております
ので、その保証の取り扱いなども検討する必要があります。
例えば、第三者に事業譲渡を行なう場合、数年は連帯保証人として、残るのか
あるいは、すぐに連帯保証人から外れるのか等、相手先との交渉、銀行との話合い等
も必要となってきます。
その他、借入に当って、不動産に抵当権等設定されている場合も多いと思いますが、
その抵当権抹消のための交渉なども必要となります。
金融機関との折衝に当たりまして、税理士事務所に相談などされることをお勧めします。
お問合せはこちら

お気軽にご相談ください
お電話でのお問合せはこちら
03-5211-5945
営業時間:月~金 9:00~18:00 (祝日除く)
どのような内容のものでも、
とりあえず、対応させていただきます!
(税務相談は来所相談に限ります)